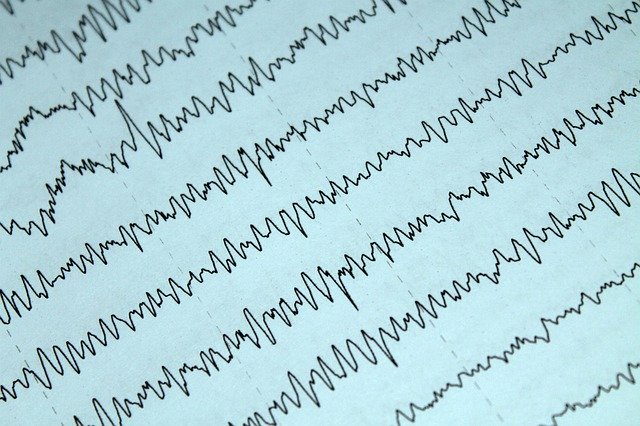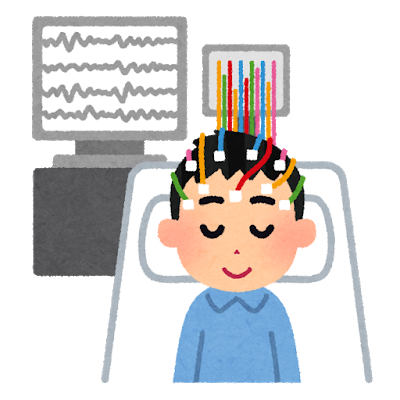ここでは脳波読影の基本について書いていきたいと思います。
ここでの脳波とは頭皮記録での脳波のことを指します。
波の構成要素
波の構成要素は、「高さ」と「幅」です。
脳波における「高さ」は、電位の変化について記録しており、脳波の場合はμVが単位になります。
振幅が高ければ高振幅、低ければ低振幅になります。
「幅」は、1秒間に繰り返し出現することを示す周波数(Hz)を指します。
周波数によりα波、β波、θ波、γ波、δ波に分類されます。
脳波の計測・表示法
各電極は、国際10-20法で頭皮に装着していきます。
電極の表示は各種モンタージュにより行っていきます。
大きく分けて基準導出法(単極誘導法)と双極誘導法になります。
どちらのモンタージュも相対的な電位差を記録していることが重要です。
上向きが陰性、下向きが陽性になります。
脳波の読影
脳波の読影の際に、改めて意識したいのが脳波の記録法とそれによる脳波の限界です。
それは脳の活動そのものを見ているわけではなく、頭皮に接着した電極同士の電位差をみている、という点です。
頭皮に付けた電極のため、清拭やペーストを用いていても汗など頭皮の状態の影響を受けます。
また、電極の電位差をみているという点に関しては、常に何を基準として導出しているのか読影の際には意識する必要があります。
例えば、基準導出法であれば耳朶の活性化などがその代表になります。
脳波読影のプロセスは、主に「背景波の評価」と「異常波の検出」です。
「背景波の評価」は、覚醒・睡眠の評価(覚醒度の評価)、左右差の評価などで行います。
異常波は、背景波から突出して目立つ波です。
異常波の種類は棘波(spike)、鋭波(sharp wave)、棘徐波(spike and wave)、徐波(slow wave)などがあります。
賦活法
通常は光刺激や過換気などの賦活を行っていますので、その評価も行います。
アーチファクト
各種アーチファクトに注意して読影をしていきます。
アーチファクトは、脳活動による記録ではない電位変化が混入していることを指します。
筋電図、汗による基線の変化、心電図、瞬目などによる眼球運動の混入などが有名です。
てんかん性異常波
てんかん性異常波はいくつか種類があります。
先鋭な波形のてんかん性異常波は大きく鋭波(sharp wave)、棘波(spike)に分けられます。
鋭波と棘波は幅で区別され、鋭波は200ms以内、棘波は70ms以内です。
双極誘導であれば、位相逆転(phasal reverse)を確認します。
棘波が連続すると多棘波(polyspike)と呼ぶことがあります。
また、棘波・鋭波はそのあとに徐波を伴い棘徐波、鋭徐波を形成することがあります。
異常波を認めた時に、それがどの部位に最大があるのか、全般性なのか、左右半球の同期性はどうなのかを評価します。
また、その頻度がどうなのかを評価します。
Youtubeにてんかん性異常波について解説している動画がありましたのでリンクします。
過換気
3分間と5分間の過換気で比較した検討
5分間の過換気における、最後の2分間で16%の発作,30.4%のinterictal EEG abnormalities, 30%のepileptiform dischargesが誘発された。
Craciun L, Varga ET, Mindruta I, Meritam P, Horváth Z, Terney D, Gardella E, Alving J, Vécsei L, Beniczky S. Diagnostic yield of five minutes compared to three minutes hyperventilation during electroencephalography. Seizure. 2015 Aug;30:90-2. doi: 10.1016/j.seizure.2015.06.003. Epub 2015 Jun 14. PMID: 26216691.
3分間の過換気は本当に必要?
85%の欠神発作は過換気開始から1.5分以内に起こっていた。
Watemberg N, Farkash M, Har-Gil M, Sezer T, Goldberg-Stern H, Alehan F. Hyperventilation during routine electroencephalography: are three minutes really necessary? Pediatr Neurol. 2015 Apr;52(4):410-3. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.12.003. Epub 2014 Dec 31. PMID: 25661285.
今後、追記をしていく予定です。